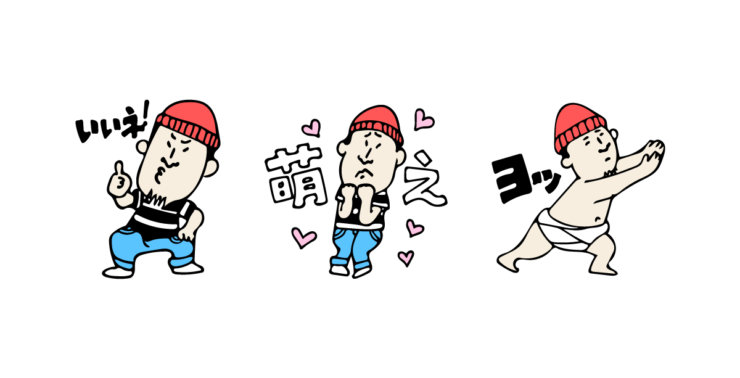2月のある日のこと。年末年始にあった出来事をきっかけに、改めて自分の内省力のなさを感じていながらも、何も対策が打てていなかった僕は、1つのことを思いつきました。
「GitHub と Cursor を活用して、AI と対話しながら振り返りができるツールを作ってみたらどうだろう」
正直、この思いつきがプログラミング教育に対する僕の考え方を180度変えることになるとは、その時は全く想像もしていませんでした。
目次
AIファーストで学ぶということ
課題があるから学ぶ、という自然な流れ
従来のプログラミング学習って、まず基礎を学んで、次に応用を学んで、そして実践に移る、みたいな順序が定番でしたよね。
でも、AIとの対話を通じて気づいたんです。「課題発見 → 解決 → 改善」というサイクルを、めちゃくちゃ自然に回せるということに。
僕の場合で言えば「課題」は内省力のなさでした。
そして、それを解決するために、僕はCursorエディタを使って以下の方法を使いました。
- まずAIに振り返りを話す
- AIをコーチ役にする
- そして、AIの挙動を自分の思い通りすべくひたすら改造していく
自分が切実に解決したいことに対して、今までの僕は「すぐ試してみる」ができませんでした。
でもAIツールの良さは「すぐ試せる環境」がそこにあることです。
多少の課金をすれば、なんとかなる。あーだこーだいって悩みがちな方には本当おすすめです。
実際、僕もCursorエディタを使って振り返りツール化を試しましたが、設定をAIと対話しながら段階的に改善していきました。
「こうしたい」って要望を伝えると、AIが提案してくれて、実装してみて、また改善する。
このプロセスの中で、気づいたらツールの使い方や設計の考え方が身についているんですよね。これが本当の高速でODCAを回すということなんだと思いました。
テストから見えた、AIとの付き合い方
実際にCursorを使った振り返りのを実施してみたら、いろいろ面白い発見がありました。
AIの時間認識に関する制限とか、週間・月間目標の参照方法における課題を多々見つけました。
でも、これらは単なる技術的な制限じゃなくて、「AIが苦手なこと」「AIがカバーできないこと」を理解する重要な機会だったんです。
AIは万能じゃない。でも、それって新しい道具との出会いにおいて当然のことですよね。
人類が火を発見した時だって、それは万能の道具じゃなかったけど、使い方を学ぶことで文明を大きく前進させた。AIも同じだと思うんです。
プログラミング教育の現場で考えたこと
「それってAIでよくない?」という問いかけ
プログラミングと起業の学校・ジーズアカデミーでメンタリングをしていて、ふと考えることがあるんです。
今後、生徒から「それってAIでよくない?」って問いが増えてくるんじゃないかって。
確かに、多くの作業はAIが代替できるようになるでしょう。
でも、だからこそ人間の創造性がより重要になってくると思うんですよ。AIは僕たちの創造性を奪うんじゃなくて、むしろ拡張してくれる存在だと感じています。
模写型学習から創造的学習へ
僕も来月プログラミング勉強会をやらせていただく機会があるのですが、ここで1つのことを試したいと思います。
従来の「みんなで同じものを作る模写型学習」から脱却して、最低限のテーマ設定の中で、個々人の創造性を引き出す場を作りたいなって。
短時間でも個別のアウトプットを生み出せる場。AIと対話しながら、自分だけの何かを作る経験。これこそが、AI時代における新しいプログラミング学習のあり方なんじゃないかと思うんです。
没頭できる喜びの発見
技術的な改善がもたらす、ワクワク感
それにしても、振り返りプロジェクトの改善に取り組む中で、久しぶりに「没頭できる喜び」を感じたんです。
GitHub との連携強化、MCPを活用した自動プル/プッシュ機能の実装、Composerの活用によるセッション開始時の改善…。
技術的な課題を一つずつクリアしていく過程って、まるでパズルを解いているような楽しさがあるんですよね。休日にFF7楽しみながらも、気づいたらプロジェクト改善に時間を使ってしまう。それほどまでに夢中になれるものに出会えたのは、本当に貴重な経験でした。
AIを「補助ツール」として活用する
重要なのは、AIを「言いなりになるツール」としてじゃなくて、「最適解を見つけるための補助ツール」として活用することだと思います。
自分にとっての最適解を探求するプロセスそのものが、学びであり、創造なんですよね。
これからの展望:ワークショップとして確立したい
個人の内省とAI活用の体系化
この1週間の実践で得られた手応えを、もっと多くの人と共有したいなって思ってます。
振り返りツールの開発を通じて得た知見を、ワークショップとして体系化して、個人の内省とAI活用方法を伝えていけたらいいなと。
人間特有の価値を見つける
AIとの共創を深めていく中で、逆に「人間特有の価値」がより鮮明に見えてきたんです。
感情の受容、他者との関係性、創造への衝動…。これらはAIには持ち得ないものですよね。
だからこそ、AIとの共創は、人間性をより深く理解する機会でもあるんだと思います。
創造をやめない、ということ
AIの登場によって、確かに多くのことが変わることは間違いありません。
でも、それは創造の終わりじゃなくて、新しい創造の始まりだと思うんです。
火の発見が人類に調理という文化をもたらしたように、AIとの出会いは、僕たちに新しい創造の形をもたらしてくれるはず。大切なのは、「創造をやめない」こと。AIと共に、より豊かな未来を創っていくこと。
振り返りツールの開発から始まった小さな気づきが、教育への新しいアプローチへとつながっていく。この経験を通じて、僕はAI時代における学びの本質を、少しずつ掴み始めているような気がしています。
今回のアイディアが、新しい学びの形につながるよう、探求していきたいと思います。