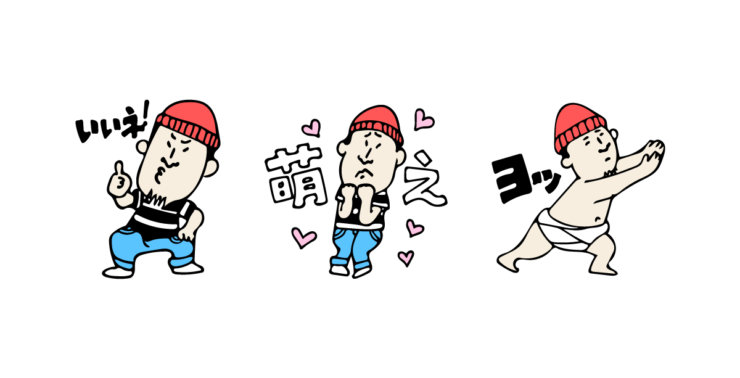このブログの中でも何度となく書いていますが、これまでのキャリアの中で、僕は教育業に携わる機会を数多く持たせていただきました。
規模は大小問わず、そして立場に関しても、講師・スタッフ・学生と全ての立場を経験してきました。
その数は25に上ります。
その中で、良い空間・雰囲気に共通しているなぁと思ったポイントと、結局は空間もAIも自分を投影する鏡となり存在しうるものなのではないか、そんなことを考えたので、ブログにまとめたいと思います。
「煩雑にモノが置かれてない」ことの影響
僕が今関わっているお仕事の中の1つに、埼玉県は大宮にある「さいたまIT・Web専門学校」という学校でのオープンキャンパスの体験授業の講師があります。
体験授業は1時間だけなのですが、最初は1年だけのお仕事の予定でした。
しかし、気づけば4月から4年目になります。大変ありがたい限りです。体験授業だけをやるというのも不思議なお仕事なのですが。笑
こちらの学校、専門学校というだけあって、入学対象は基本的に高校生が中心。高校の次の選択肢として、大学などと比較検討されるという類の学校です。
このさいたまIT・Web専門学校さん、関わらせていただく中で感じるのが、「抜群に雰囲気のいい場所」なんです!
もし僕が親戚や知り合いに高校生の子がいてITやWeb分野に興味があると言ったら、間違いなくこの学校を薦めたいと思うくらいです!
そして、なぜこの学校は雰囲気が良いのか?自分なりに考えてみたのですが…
その理由として、僕は「モノが雑然と配置されていない、とても綺麗である」ということが挙げられるのではないかと思いました。
ある意味これは施設としては当たり前なのかもしれません。それに、さいたまIT・Web専門学校さんは、比較的新しい学校ですから、綺麗で当然だと思います。
しかし、細かいモノが一時的にでも煩雑な形で置かれていることを僕は見たことがありません。
教職員室にも立ち入りさせていただいたことがあるのですが、本当にキレイなのです、ここでいう「キレイ」というのは、ピカピカに磨かれているというニュアンスというよりも、何度も書かせていただいている通り、「モノが煩雑に置かれていない」ということなのです。
こういう細かく丁寧な配慮が、学校の・空間の雰囲気をよくしてくれているんだろうんだと思いました。
実際お話を聞くと、開校してから数年、しっかりと定員を確保することができているということでした。
空間は自身を投影する鏡だ
なぜ、煩雑にモノが置かれていないと雰囲気がよくなるのか?考えてみたのですが、僕は色々な理由が挙げられると考えました。
まずモノが煩雑に置かれないということは、ルールがしっかりしているということですよね、どこに何を置くkということがしっかりと定まっている。これはルールが決まっているからこそです。
当たり前のように思うかもしれませんが、たくさんの人が行き交い、色々な対応をしていると「一旦ここに置く」といったようなことが発生しうると思います。
そして、それが放置されるということは、ルールが明確に定まってないものが存在している可能性があるわけですよね。
ルールが明確に定まってない空間に果たして雰囲気の良さが生まれるのか…というと、僕はその方程式は成り立たないと思いました。
ルールが定まってない?自由でかつ自立性があっていいじゃないか、それでも雰囲気のいい場所はあるはずだという意見もあるかもしれません。
しかし、学校などの学舎というのは、もちろん学生さん各々で進路や将来への展望は異なると思いますが、どんな未来であれ、未来に向かって学ぶというのは自分を律することができないと僕は考えます。学ぶということは律することそのものだとさえ思うからです。
その実現に一役担うのが、僕は「ルール」だと思っています。
だからこそ、さいたまIT・Web専門学校さんは中のルール作りがしっかりとなされているんだと見て取れました。
実際、学生さんの雰囲気もめちゃくちゃ良いんですよね…。
そして、そう考えると空間というのは、まさに自分たちの考えやポリシー、今の状態を投影する鏡なのではないかと思ったのです。
はてさてAIはどうだ?AIも自分を映す鏡となりうるのではないか?
さて、話を移して、ここ最近何かと話題のAIを見てみましょう。
僕はこのAIでさえも、自分の内面を投影する鏡となり得るのではないかと思うのです。
僕自身は、AIは「自分の仕事のパートナー」としてとらえている側面があります。
相談、一部のタスクを依頼するパートナー、そのような感じですね。
そして、そのような仕事のパートナーに対して何かを依頼するというのは、自分が仕事を依頼するスキルが大きく問われると考えます。
AIが思った通りに動かない?それはもちろんAIの性能に依存するところもありますが、そこも含めて自分の判断・そして依頼のスキルが鍵を握っていると考えます。
AIにタスクを依頼しないこともスキル。的確に細かく伝えることもスキル。
「AIが言ってることが全て正しい」と妄信するのは、自分が「依存する姿」を投影した結果なのではないかとさえ思うのです。
もちろん我々人間各々が全て正しいとも限りません、人間ですから間違うことがあって当然。
だけど、AIになったら急に疑うことがなくなるというのは、僕は危険だと考えています。そこには「依存」という自分の心が投影されていると考えているからです。
AIを使っているときも俯瞰して自分を見ること、これが大事なんだと思っています。
まとめ
ということで、今回は2つの切り口で「全ては自分を移し出す鏡」という話を書かせていただきました!